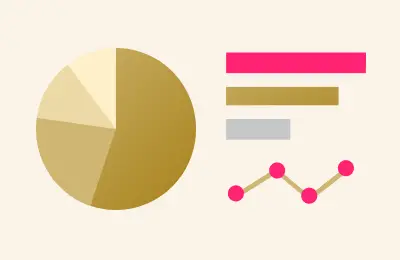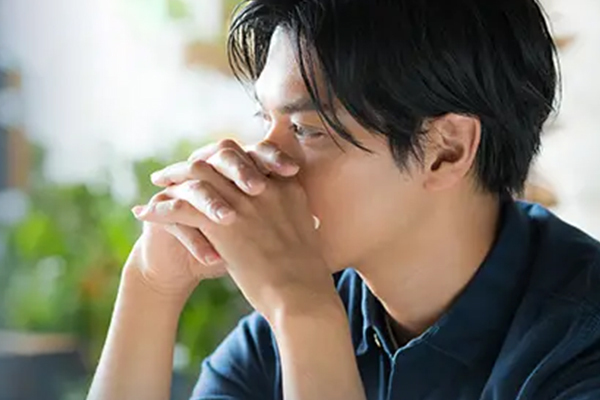- 結婚相談所のツヴァイ
- 婚活Times
- 婚活
- 事実婚と同棲の違いとは?メリット・デメリットから手続きまで徹底比較
事実婚と同棲の違いとは?メリット・デメリットから手続きまで徹底比較

「結婚する?それとも、まずは一緒に暮らしてみる?」
27歳独身の筆者Sも、友人との会話で結婚や同棲が話題になることが増えました。
パートナーとの将来を考えたとき、まずは「同棲」が思い浮かぶかもしれません。
それに加え、最近は「事実婚」という選択肢をとるカップルも増えていますが、この2つの違いを正しく説明できますか?
この記事ではツヴァイ編集部Sが、似ているようで全く違う「事実婚」と「同棲」について、法的な権利の違いからメリット・デメリット、必要な手続きまで徹底比較します。
この記事を読んでわかること ・事実婚と同棲の違い ・事実婚と同棲のメリット・デメリット ・事実婚をする前に確認するべきこと ・事実婚に関するよくある質問 ・自分に合うパートナーシップの見つけ方
この記事が、あなたとパートナーにとって最適な関係性を見つけるためのヒントになれば嬉しいです。
1.事実婚と同棲の決定的な違いを比較

「事実婚」という言葉は、最近よく耳にするようになりましたよね。
パートナーと一緒に暮らすという点では同じように思える「事実婚」と「同棲」。
でも実は、法律上の扱いも社会的な意味も大きく異なります。
「将来を考えた時、自分たちにはどの形が合っているのかな?」
いざ自分のこととなると、どちらがしっくりくるのか迷ってしまいますよね。
ここでは、2つの違いをはっきりさせて、それぞれの関係性が持つ意味を一緒に考えていきましょう。
一番の違いは「夫婦になる意思」と「社会的届け出」の有無
事実婚と同棲の一番の違いは、「お互いに夫婦になる」というはっきりした意思があるか、そしてその意思を社会的に示す「客観的な事実」があるかどうかです。
事実婚:
婚姻届は出さないけれど、二人の中に「夫婦として一緒に生活していく」という強い意志があり、その関係性が客観的な事実で裏付けられている関係のことを言います。
客観的な事実とは、例えば以下のようなものを指します。
・結婚式を挙げたり、親族や友人に「夫婦」として紹介している
・家計をひとつにして生計を共にしている
・住民票の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」と届け出ている
こうすることで、二人の関係はただの同居人ではなく「法律上の結婚に準じた関係」として扱われることが多くなります。
同棲:
こちらは一般的に、単に「一緒に住んでいる」状態を指します。
必ずしも二人ともが夫婦になることを決めているわけではありません。
社会的な届け出もしないので、法律上は「他人同士の共同生活」と見なされて、法的な保護や権利はほとんどありません。
二人の間に夫婦としての気持ちがあって、それを証明する事実があるかどうかが、法的に守られるかどうかの大きな境界線になるんです。
権利と義務の違い早わかり比較表
事実婚と同棲では、受けられる法律の保護や、負うべき義務にどれくらいの違いがあるのでしょうか。
比較のために「法律婚」も加えて、下の表で具体的に見てみましょう。
|
項目 |
事実婚(内縁) |
同棲 |
法律婚 |
|---|---|---|---|
|
扶養の義務 |
あり |
なし |
あり |
|
貞操義務 |
あり |
なし |
あり |
|
健康保険の扶養 |
入れる |
入れない |
入れる |
|
国民年金の第3号被保険者 |
なれる |
なれない |
なれる |
|
遺族年金の受給 |
できる |
できない |
できる |
|
財産分与 |
請求できる |
請求できない |
請求できる |
|
不貞行為の慰謝料請求 |
請求できる |
請求できない |
請求できる |
|
法定相続権 |
なし |
なし |
あり |
|
税金の配偶者控除 |
適用されない |
適用されない |
適用される |
|
子どもの戸籍 |
非嫡出子 |
非嫡出子 |
嫡出子 |
|
医療行為の同意 |
各病院の判断による |
原則、法的な同意権はない |
各病院の判断による |
|
住宅ローン |
利用できる場合がある |
利用できない |
利用できる |
事実婚(内縁)で権利を主張するには、「夫婦同然の生活」を客観的に示す必要があります。
*参考:いわゆる事実婚※に関する制度や運用等における取扱い
この表を見るとわかる通り、事実婚は、法律婚とほぼ同じくらいの権利と義務が認められています。
一方、相続権や税金の控除といった法律上の「配偶者」であることが前提の権利は対象外なんです。
そして同棲には、法的な権利や義務がほとんど発生しないのが大きな特徴。
もし関係を解消する時に財産分与を請求できなかったり、相手に何かあっても法的な保障が受けられなかったりと、不安定な立場に置かれてしまう可能性もあります。
2.そもそも「事実婚」とは?法律婚・内縁との関係性
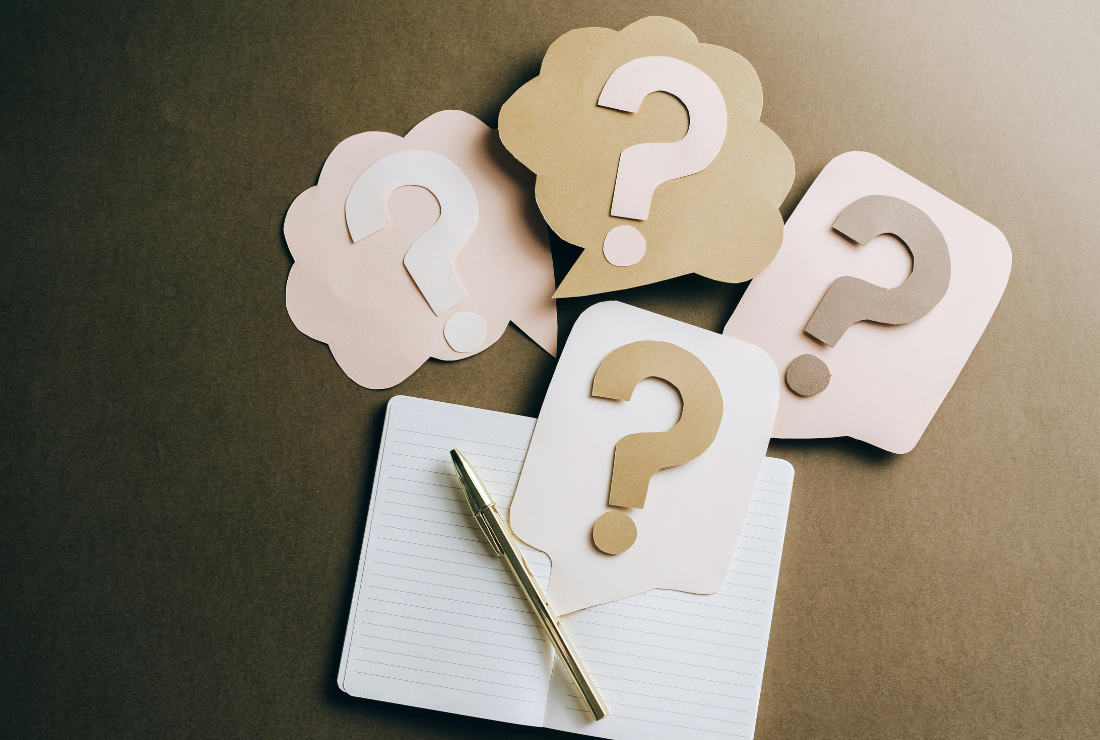
パートナーとの将来を考え、自分たちらしい形を模索する中で、「事実婚」という選択肢が頭に浮かぶ人もいるかもしれません。
しかし、婚姻届を出す「法律婚」と具体的に何が違うのか、また、似た言葉である「内縁」とどういう関係なのかを正しく理解している人は、まだ少ないのではないでしょうか。
さまざまなパートナーシップの形がある今だからこそ、二人の関係についてより良い選択をするためにも、まずは言葉の正確な意味を知ることが第一歩です。
ここでは、事実婚の基本を分かりやすく解説します。
事実婚の定義
事実婚とは、婚姻届を提出していないだけで、二人には夫婦になる気持ちがあって、実質的には夫婦同然の生活を送っている関係のことです。
法律婚が「戸籍」という形で成立するのに対して、事実婚は「夫婦としての実態」があるかどうかで判断されるのが一番の特徴。
お互いを一生のパートナーだと認め、心と暮らしの両面で支え合う、安定した共同生活を送っている状態が事実婚の本質なんです。
事実婚が法的に認められるためのポイント
では、どうすれば法的に「事実婚」と認められ、法律婚に近い保護を受けられるのでしょうか。
まず大切なのは、「事実婚は、何か一つの手続きをすれば自動的に成立するものではない」と理解しておくことです。
裁判所などが事実婚を判断する際は、「①夫婦になろうというお互いの気持ち」と「②夫婦としての共同生活の実態」があるかを、さまざまな証拠から総合的に見て判断します。
口約束だけだと、万が一関係が悪くなった時に「ただの同棲だった」と言われてしまうかもしれません。
二人の関係を確かなものにするために、客観的な証拠を一つでも多く積み重ねておくことが大切です。
二人の関係を確かなものにするために、こんなアクションが有効です。
① 住民票の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」と届け出る
これは、事実婚を証明する上で強力な証拠になります。
同じ住所に住んでいることを示すだけでなく、続柄を「同居人」ではなく「夫(未届)」や「妻(未届)」と記載することで、夫婦として生活する意思をはっきり示せます。②事実婚に関する公正証書を作成する
「事実婚契約書」といった形で、二人の夫婦としての意思や生活費の分担、財産のことなどを契約書にして、公証役場で「公正証書」として残す方法です。
法的な証明力が高く、将来のトラブルを防ぐためにもおすすめです。
また、最近は多くの自治体でパートナーシップ制度が導入されています。
二人がパートナーであることを自治体に届け出ることで、公的な証明書がもらえます。
これがあると、公営住宅への入居や病院での手続きがスムーズになることも。
パートナーシップ制度を導入している自治体は、下記から確認してみてください。
パートナーシップ制度導入自治体 | 情報データベース | 結婚の自由をすべての人に③結婚式を挙げる・周囲に夫婦として紹介する
結婚式や披露宴を行ったり、年賀状などで結婚を報告したりすることも、二人が夫婦として共同生活を送っていることの証拠となります。
親や親族、友人、職場などに、お互いを「夫」「妻」として紹介することも同様です。④家計をひとつにし、生命保険の受取人を互いに指定する
生活費を共有の口座で管理したり、お互いを生命保険の受取人に指定したりすることは、「生計を一つにして支え合っている」ことの証明になります。⑤子どもがいる場合は、父親が認知する
もし二人の間に子どもが生まれたら、父親が「認知届」を出すことで法律上の親子関係が成立します。
これも、二人が夫婦として生活していることを示す証拠の一つになります。
こうした証拠が多ければ多いほど、二人の関係は「事実婚」として法的に認められやすくなります。
「事実婚」と「内縁」はほぼ同じ意味

「事実婚」と似た言葉に「内縁」がありますが、この2つは法的に明確な区別はなく、ほぼ同じ意味で使われています。
昔から法律の世界では「内縁」という言葉が使われてきました。
「事実婚」は、夫婦別姓を希望するなど、より自分たちの意思で積極的に「籍を入れない」という選択をするカップルが使うようになった、現代的な言葉というイメージです。
どちらの言葉を使うにしても、「婚姻届は出していないけど、実質的には夫婦」という関係を指す点は同じで、受けられる法的保護も変わりません。
3.事実婚を選ぶメリット
さまざまな生き方が選べる今、なぜ「事実婚」というパートナーシップの形が注目されているのでしょうか。
それは、法律婚の枠にはまらない、独自の魅力とメリットがあるからです。
ここでは、事実婚を選ぶことで得られる4つの主なメリットを見ていきましょう。
①夫婦別姓を選択できる
事実婚を選ぶ一番の理由として挙げられるのが、夫婦別姓を実践できることです。
今の日本の法律では、結婚する時に夫婦どちらかの姓に統一する必要がありますよね。
でも、仕事で築いてきたキャリアや名前を大切にしたい方にとって、姓を変えるのは大きな負担になることもあります。
また、銀行口座や免許証など、名義変更の手間は想像以上にかかるものです。
筆者Sも自分の苗字が気に入っているので、自分の名前でキャリアを重ねていきたいなと思ったり、すでに結婚した友人たちは何も抵抗なかったのかな?と感じています。
事実婚は、個人のアイデンティティやキャリアを尊重し、対等な関係を築きたいと願うカップルにとって、とても大きなメリットだと言えます。
②お相手の親族との法的な姻戚関係が発生しない

法律婚をすると、パートナーの親や兄弟姉妹と「姻族」という法的な親戚関係が生まれます。
これにより、特別な事情がある場合は、お互いの親族を扶養する義務が生じる可能性もあるんです。
一方、事実婚の場合は婚姻届を出さないので、この法的な姻戚関係は発生しません。
パートナーの大切な家族として良い関係を築くことは大切ですが、法的な義務からは自由でいられます。
「家同士」というより「個人同士」のパートナーシップを大切にしたいカップルにとっては、気持ちが楽になるポイントかもしれません。
③関係を解消しても戸籍に記録が残らない
二人の関係が終わりを迎えた時のことも考えてみましょう。
法律婚の場合、離婚すると戸籍にその記録が残ります。
事実婚はもともと戸籍の手続きをしていないので、関係を解消しても、戸籍には何も記録が残りません。
将来のライフプランを考えた時に、戸籍がクリーンな状態であることを重視する方にとっては、これも一つのメリットに感じられるでしょう。
④法律婚とほぼ同等の社会的保障が受けられる
「籍を入れないと、パートナーに何かあった時に何も保障されないんじゃない?」
と不安に思う方もいるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
事実婚は「同棲」とは違い、法律婚に近い多くの社会的保障を受けることが可能です。
詳しくは、前述したこちらの比較表を確認してみてくださいね。
こうした保障は、生活の基盤を守る上でとても大切です。
一部対象外のものはありますが、日常生活の多くの場面でセーフティネットが機能するのは、事実婚の大きな強みと言えるでしょう。
4.事実婚で注意すべき5つのデメリット

事実婚には、個人の生き方を尊重できるメリットがたくさんある一方で、もちろん注意すべき点もあります。
「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、決断する前に知っておくべき5つのことをお伝えします。
①法定相続人になれず、遺産相続ができない
事実婚で、注意が必要なデメリットの一つが相続権の問題です。
法律婚の夫婦なら、パートナーは「法定相続人」として遺産を相続する権利がありますが、事実婚のパートナーにはこの法定相続権が一切ありません。
何十年も連れ添い、一緒に財産を築いてきたとしても、もし遺言書がなければ、財産は相手の親や兄弟姉妹に渡ってしまいます。
最悪の場合、住んでいた家を出ていかなければならない、ということにもなりかねません。
このリスクを避けるためにも、パートナーがお互いに「遺言書」を作成して、財産を相手に残す意思をはっきり示しておくことが必要です。
②税金の配偶者控除・扶養控除が適用されない
税金の面でも、事実婚は法律婚と扱いが異なり、法律上の夫婦なら受けられる「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が適用されません。
これにより、法律婚の夫婦と比べると、世帯全体で納める税金が多くなる可能性があります。
また、生命保険料控除や医療費控除も家族分を合算して申告することができないので、税金の負担が少し重くなる場合があることは知っておく必要がありますよ。
③子どもは「非嫡出子」となり、父親の認知が必要

もし二人の間に子どもが生まれた場合、その子の法律上の立場にも違いが出てきます。
法律婚の夫婦の間に生まれた子は、自動的に夫婦の「嫡出子」になりますが、
事実婚のカップルの間に生まれた子は「非嫡出子(婚外子)」となり、そのままでは母親の戸籍にしか入れません。
父親が法律上の親になるためには、役所に「認知届」を提出することが必要です。
認知をして初めて、子どもは父親の財産を相続したり、養育費を受け取ったりする権利が生まれるので、子どもの将来のためにも必ず話し合っておきましょう。
④親や周囲から理解を得にくい場合がある
事実婚は少しずつ社会に広まってきてはいますが、まだ全ての人に受け入れられているわけではありませんよね。
特にご両親の世代からは、「どうして籍を入れないの?」と心配されて、なかなか理解を得られないケースも少なくありません。
だからこそ、なぜ自分たちがこの形を選ぶのか、その理由や覚悟について二人で意思を固めて、周りの人たちに誠実に説明していく姿勢が大切になります。
もし筆者Sが両親に「籍を入れないことにした」と伝えたら…と考えると、とても心配されそうで正直緊張します。
パートナーとの結束力が試されるポイントだなと感じました。
⑤手術の同意など、法的な夫婦として扱われない場面がある
パートナーの命に関わるような緊急の時にも、事実婚の弱点が出ることがあります。
例えば、パートナーが事故や病気で手術が必要になった時、病院によっては「法律上の家族ではない」という理由で、手術の同意書にサインさせてもらえない可能性があるんです。
最近は柔軟に対応してくれる病院もありますが、法的な決定権がないため、最終的には病院の判断に委ねられてしまいます。
対策として、元気なうちに「任意代理契約」などを公正証書で結んでおくのも、お互いを守るための有効な方法ですよ。
5.同棲のメリット・デメリット

将来を考えるカップルにとって、同棲は自然なステップの一つですよね。
これまで事実婚について見てきましたが、比較対象として「同棲」のことも正しく理解しておくのが大切です。
ここでは、同棲のメリット・デメリットについて見ていきます。
同棲のメリット|結婚生活のシミュレーションができる
同棲の一番のメリットは、本格的な結婚生活の「お試し期間」として、お互いの相性をじっくり確認できる点です。
デートだけでは見えてこない、以下のような日常生活での価値観を知る機会になるんです。
・生活リズムや習慣の違い:朝型か夜型か、休日の過ごし方、掃除の頻度など、一緒に心地よく暮らせるかを確認できます。
・金銭感覚:何にお金を使い、何を節約したいか。生活費を分担する中で、お金に対する価値観を確認できます。
・食の好みや家事の分担:毎日の食事の好みや家事への考え方を知って、協力し合えるかがわかります。
もちろん、一緒に過ごす時間が増える安心感や、家賃や生活費を分担できる経済的なメリットもあります。
「この人となら、一生一緒に歩んでいけるかな?」
その最終確認をするための、貴重なシミュレーション期間になるでしょう。
同棲のデメリット|法的な保護や権利はない
一方同棲の一番のデメリットは、二人の関係を守るための法的な保護や権利がないという点です。
事実婚が「結婚に準ずる関係」として法律で守られるのに対して、
同棲は法的には「他人同士の共同生活(ルームシェア)」と同じ扱いになります。
そのため、以下のような場面でとても弱い立場になることを理解しておきましょう。
・別れても財産分与は請求できない:長く一緒に暮らして貯金や家具を揃えても、法律上、財産分与を求める権利はありません。
・浮気されても慰謝料は請求できない:法律上の貞操義務がないので、原則として相手の浮気の責任を問うことはできません。
・健康保険の扶養に入れず、遺族年金も受け取れない:社会保障の上では「配偶者」とは見なされません。
・相手に何かあっても相続権はない:パートナーが亡くなっても、遺産を受け取ることはできません。
また、法的な区切りがない分、結婚へのステップが曖昧になってしまうリスクもあります。
6.事実婚をする前に確認しておくべきこと
事実婚は二人の意思を尊重する自由な形ですが、「婚姻届を出さない」からこそ、事前に二人でしっかり話し合って決めておくべきことがたくさんあります。
「言わなくてもわかるはず」という思い込みは後々のトラブルの原因になりかねないので、
後悔しない選択のために、6つのポイントについて真剣に考えてみましょう。
お金のこと

生活の基本となるお金の問題は、一番大切な確認事項と言えます。
曖昧にせず、具体的なルールを決めておきましょう。
・生活費の分担:収入に応じるか折半するかなど、毎月の生活費はどのように分担しますか?
・貯蓄と財産:二人の貯金はしますか?車や家など大きな買い物をした時、名義や所有権はどうしますか?
・財産分与:もし関係を解消することになったら、二人で築いた財産をどう分けますか?
お金に関する約束事は「事実婚契約書」として書面に残し、法的な証明力を持つ「公正証書」にしておくと安心です。
子どものこと
将来子どもを望むなら、その子の権利と未来を守るために必ず確認が必要です。
・認知:事実婚で生まれた子と父親の親子関係を法律で結ぶには、父親による「認知」が絶対に必要です。
認知がないと、子どもは父親の相続人になれず、養育費を請求する権利も法的には発生しません。・親権:子どもの親権は、原則として母親の単独親権になります。
・姓(名字):子どもの姓は、原則として母親の姓になります。父親の姓にしたい場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。
住まいのこと
二人の生活拠点となる住まいについても、契約や名義の問題をクリアにしておきましょう。
・賃貸契約:どちらか一方の名義で部屋を借りる場合、大家さんや管理会社に相談して、続柄を「妻(未届)」などと記載できないか確認してみましょう。
・住宅ローン:最近は、事実婚カップルでも組めるペアローンなどが増えていますが、金融機関によって対応が違うので事前の確認が必須です。
もしもの時のこと

どちらかが病気になったり介護が必要になったりした時、お互いを支え合える準備をしておくことが大切です。
・病気や手術の同意:パートナーが入院して手術が必要になった時、法律上の家族ではないため手術の同意がスムーズにいかない可能性があります。
・介護:パートナーの介護が必要になった時、介護休暇などが取れるか、職場のルールを確認しておく必要があります。
いざという時のために、お互いを代理人として指定する「任意代理契約」などを公正証書で作成しておくと安心です。
相続のこと
事実婚のデメリットで一番大きいのが相続の問題です。
・法定相続権がないことの再確認:事実婚のパートナーには、一切の法定相続権がありません。
・遺言書の作成:パートナーに財産を残すための、唯一確実な方法が「遺言書」です。お互いに財産を遺す旨を記した遺言書を、必ず作成しておきましょう。
これも、法的に確実な「公正証書遺言」の形で残すのが一番ですよ。
周囲との関係
二人の間の合意はもちろんですが、社会的な関係についても話し合いが必要です。
・親族への説明:親や親族に、事実婚という選択をどう説明して、理解してもらうか考えておきましょう。
・職場での扱い:会社の慶弔休暇や家族手当などの福利厚生が、事実婚パートナーにも適用されるか、就業規則を確認しておくことが大切です。
7.事実婚に関するよくある質問(Q&A)

ここまで事実婚のメリット・デメリットや、事前に確認すべきことについて解説してきました。
ここでは、多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式で見ていきましょう。
Q. 事実婚でも健康保険の扶養に入れますか?
A. はい、入れます。
事実婚のパートナーでも、法律婚の夫婦と同じように健康保険の被扶養者になれます。
もちろん、収入などの条件を満たす必要はあります。
手続きの際には、「事実婚関係を証明する書類」の提出を求められるのが一般的です。
住民票の続柄を「夫(未届)」などにしておくとスムーズですよ。
Q. 相手の生命保険金は受け取れますか?
A. はい、受け取れる可能性が高いです。
最近では多くの保険会社が、一定の条件を満たせば事実婚のパートナーを受取人に指定することを認めています。
「生計が同じこと」などが条件になることが多いので、保険に加入する時や見直す時に、保険会社にしっかり確認しましょう。
*参考:内縁の妻・夫も生命保険の受取人に指定できる!注意点や条件とは?
Q. 事実婚を解消する際、財産分与や慰謝料は請求できますか?
A. はい、請求できます。
事実婚は法律上「結婚に準ずる関係」と見なされるので、関係を解消する時も法律婚の離婚と同じように考えられるんです。
・財産分与: 二人で協力して築いた共有財産は、財産分与の対象になります。
・慰謝料: 相手が原因で関係が壊れた場合は、慰謝料も請求できます。
ただし、そのためには二人が「事実婚だったこと」を証明する必要があります。
Q. 相手に不貞行為があった場合、慰謝料は請求できますか?
A. はい、請求できます。
事実婚の二人にも、法律婚の夫婦と同じように「貞操義務」があるとされています。
もしパートナーが浮気をして関係が壊れた場合は、パートナーとその相手に対して慰謝料を請求することができるんです。
Q. クレジットカードの家族カードは作れますか?
A. カード会社によりますが、作れる場合が増えています。
最近は社会の変化に合わせて、事実婚のパートナーにも家族カードの発行を認める会社が増えつつあります。
利用したいカード会社の公式サイトを確認したり、直接問い合わせてみたりするのが確実です。
*参考:別姓のパートナーも家族カードの申し込みはできますか? | よくあるご質問(個人・法人のお客様)
8.「事実婚」と「法律婚」自分に合うパートナーシップの見つけ方

ここまで読んでみて、「自分にはどのパートナーシップの形が合っているんだろう?」と考え込んでしまう方もいるかもしれません。
大切なのは、あなたが何を大切にしたいかを深く理解し、その価値観を分かち合えるパートナーを見つけることです。
ここでは、あなたらしいパートナーシップを見つけるための、3つのステップをご紹介します。
Step 1:自分自身の「ものさし」を明確にする
まずは、パートナーシップで何を優先したいのかをはっきりさせてみましょう。
・姓が変わることについて、どう考えますか?
どうしても自分の姓を維持したいですか?
それとも、パートナーと同じ姓になることに喜びを感じますか?・法的な保障をどのくらい重視しますか?
相続権や税金の控除といった、法律で守られた安定性の重要度はどのくらいでしょうか?・周囲との関係性をどう築きたいですか?
ご両親や親族からの理解を大切にしたいですか?
それとも、二人の意思を尊重することを優先しますか?
これらの問いにじっくり向き合うことで、あなたの「ものさし」が見えてくるはずですよ。
Step 2:パートナーとの対話を深める
もし今パートナーがいるなら、次はその「ものさし」を二人で共有し、すり合わせていくことが不可欠です。
お金のこと、子どものこと、もしもの時のこと。
この記事でお伝えしてきたテーマについて、オープンに話し合ってみましょう。
Step 3:同じ価値観を持つパートナーと出会う
「自分は事実婚もいいなと思う」「やっぱり普通の法律婚かな」
「自分の考えを理解してくれる相手と出会うにはどうすればいいんだろう?」
この記事を読んで、こんな風に感じている方もいるかもしれません。
自分らしいパートナーシップを築くには、まず同じ方向を向ける相手と出会うこと。
出会いの方法はさまざまですが、結婚という未来を真剣に考えるなら、最初からお互いの価値観を率直に話せる場で相手を探すのが近道です。
特に、さまざまなパートナーシップの形に理解がある人と出会いたい場合、結婚相談所のようなサービスは、価値観の合う相手と効率的に出会うためのひとつの選択肢になります。
例えば、結婚相談所ツヴァイは、一人ひとりの結婚観やライフプランに真摯に寄り添い、婚活をサポートしています。
また、ツヴァイが実施している婚活診断では、自分の簡単な情報とお相手の希望条件を入力するだけで、実際の会員の中からあなたの条件に合う人のプロフィールを確認することができるんです。
実際の情報を見ると、あなたの結婚観ももう少し具体的にイメージできるようになることもあります。
まずは、新しい一歩を踏み出してみませんか?
9.【まとめ】事実婚も法律婚も、あなたらしい選択を
今回は、「事実婚」と「同棲」の違いから、それぞれのメリット・デメリットまで、さまざまなパートナーシップの形を一緒に見てきました。
個人の意思を尊重し、対等な関係を築く事実婚。
法的な保護のもと、安定した未来を描く法律婚。
そして、将来へのステップである同棲。
どの形が優れているというわけではありません。
一番大切なのは、あなたが何を望み、どんな人生を歩みたいかを考え、その価値観を共有できるパートナーと出会うことです。

もし今、その大切な未来を共に歩むパートナーを探しているのであれば、一人で悩まず、出会いの専門家の力を借りるのも一つの方法ですよ。
たとえば長年の実績を誇る結婚相談所ツヴァイでは、丁寧なカウンセリングを通じて、一人ひとりの価値観に合ったお相手探しをサポートしています。
マッチング無料体験では、婚活の最新情報を知るだけでなく、お相手検索で実際の登録者を見ることもできます。
どのような可能性があるのか、気軽に体験してみませんか?
この記事の監修者
ZWEI編集部
特別記事


人気ランキング
関連記事
最新記事
カテゴリから探す
ツヴァイでは年間5,427名の方を
成婚へ導いています(※)
※2018年3月〜2019年2月の1年間に交際・婚約・結婚を理由に退会届を当社に提出されたお客さま(会員同士・会員外)